お祭り好きの皆様こんにちは!
日本全国には数多くの祭りがありますが、その中でも「奇祭」として名高いもののひとつに、大分県国東市で毎年10月14日に行われる【ケベス祭】があります。
起源や由来に関しての記録がなく謎の多い奇祭、ケベス祭。
仮面をつけたケベスがシダを燃やした炎に突進、それを阻止するトウバ。
9回目の突進で、ケベスは炎に飛びこむと、トウバたちが差又の先にシダの束を突き刺し、参拝者に火の粉を浴びせる。 pic.twitter.com/YIVbsb5xNs— 鳥居 (@shinmeitorii1) October 16, 2023
櫛来社(岩倉八幡社)を舞台に行われるこの祭りは、火をテーマとする迫力ある儀式と不可思議な伝統文化で多くの人を引きつけています。
特に、木彫りの面をかぶる「ケベス」と白装束の「トウバ」が火を巡って対峙する様子は、ほかではなかなか見ることのできない光景と言えるでしょう。
読むだけでなく五感すべてで楽しめる魅力を秘めたこの祭りについて、今回の記事ではケベス祭2025の見どころ、歴史、アクセス、過ごし方、さらには地元ならではの情報も含めてご紹介しますので、お楽しみに!
ケベス祭2025とは? 由来と魅力
歴史と起源
ケベス祭は、国東市国見町櫛来(くしく)に鎮座する櫛来社(岩倉八幡社)で、毎年10月14日の夜に奉納される火祭りです。
その起源や由来は定かではないとされており、祭り名「ケベス」の語源も複数の説があると伝えられています。
かつて旧暦9月14日に行われていたという説もあり、そのため「九月祭」と呼ばれた可能性が言われることもありますが、確証はありません。
加えて、この祭りは、2000年12月25日に国の選択無形民俗文化財に指定されています。
奇祭たる所以
ケベス祭は、その儀式のユニークさからしばしば「奇祭」と形容されます。
神事の中心には、白装束をまとった「トウバ(当場)」と、奇怪な木彫りの面をつけた「ケベス」が火をめぐって攻防を繰り広げる演出が据えられています。
夕闇の中、境内に積まれたシダの束に火が灯されると、ケベスは機を見て火の中に突入を試み、トウバはこれを阻止しようとします。
最終的には、ケベスは9度目の試みで成功してシダの山をかき回し、火の粉を散らします。
その後、トウバも火をつけたシダを持って境内を駆け巡り、観客に火の粉を浴びせる場面がクライマックスとなります。
この火の粉を浴びることには、無病息災の願いが込められていると伝えられています。
トウバは、国見町内の10の集落が毎年順に当番を務め、潔斎や準備を担います。
儀式に入る前には海での禊ぎ(海清め)を行うという記録もあります。
大分県の奇祭「ケベス祭」を見に行きました
とんでもない祭りですそして何の神様を祀っているのかわからないのがとても奇妙! pic.twitter.com/5tHFGur3Eb
— コワゾー@怖くてゾッとする体験型ホラー (@kowazo_horror) October 14, 2024
火祭りとしての見どころ
ケベス祭の見どころは、まず火を灯す瞬間と、その後の「突入・防御・火の乱舞」の流れにあります。
火が焚かれた後、ケベスが火の中に突入を試み、それをトウバが阻む攻防戦が何度も繰り返されます。
やがてケベスが火を制すると、シダの束を操って火の粉をまき散らし、さらにトウバも火を持って動き回り、参拝者に火の粉を浴びせます。
観客は火の粉を避けつつ、祭りの緊張と熱気を肌で感じることになります。
最後には、ケベスが藁束(ワラヅト)を地面に打ちつけ、翌年の五穀豊穣や吉凶を占うという所作も残ります。
地域文化としての意義
ケベス祭は、国東地域における重要な伝統行事の一つであり、地域住民が代々継承してきた祭りでもあります。
10集落が順繰りで当番を務める方式は、地域共同体の結びつきを象徴しています。
観光的にも注目され、訪れる人々に地元文化を体感させる機会となっています。
ケベス祭2025の屋台と穴場スポット情報
今年のケベス祭の屋台の情報は発表されていませんので、調べられた実例と体験記に基づく「可能性ある情報」をもとにした案内です。
屋台グルメ(出店例・予想される品目)
公式資料では、屋台の具体的なメニューまで詳細には紹介されていません。
ただし、過去の祭り報告では、「市内外から35店」が農産物や加工品を軽トラックを使って販売したという記録があります。
また、体験記などでは「パン・おにぎり・漬物・お土産・手作り品」などが並んでいたとの情報もあります。
こうした事実と前例を踏まえると、ケベス祭で見られる(あるいは期待される)屋台グルメ例を挙げるなら以下のようなものが想定されます:
- 地元産の野菜・果物加工品(漬物、ジャムなど)
- おにぎり・パン・軽食類
- 菓子類・お土産品
- 加工食品・地元産品(干物、海産加工)
- 飲み物類、菓子・甘味系

どんなお祭りでも屋台はやっぱり楽しみだよね
観覧スポット・おすすめ位置取り
観覧のためのベスト位置という記述は見当たりません。
ただ、国東市のケベス祭紹介ページでは、次のような流れが示されています:
- 夕闇に包まれた境内で、海で禊ぎをしたトウバが白装束で集まり、行列を構える。
- 境内の一隅に積まれたシダに火がつけられ、行列が乱れてケベスが突入を試み、最終的に火の粉を散らす。
- その後、トウバも火のついたシダを持って境内・外を駆け回り、参拝者は火の粉を避けながら見物する。
この流れを前提に、観覧位置の案を挙げると以下のようになるでしょう
- 境内近く:火の山の点火・突入・火の粉散布の迫力を最も近くで感じられる可能性が高い。ただし混雑・安全性を考慮して余裕を持った位置づくりが必要。
- やや離れた高所:境内全体を俯瞰的に見渡せるような小高い丘や段差のある場所があれば、火の動き全体を把握しやすくなる可能性がある(ただし現地の地形・視界に依存)。
- 境外・外周から:火の粉が及びにくい位置を選ぶ安心感はあるが、迫力の一部は遠くなる可能性あり。
これらはあくまで予想・観賞者体験に基づく案であり、実際の祭場レイアウトや混雑状況で変動します。
早めに現地入りして周囲の地形・参道・位置関係を確認して場所を決めるのが安全でしょう。
子ども連れ・安全配慮と観覧支援
ケベス祭は火の粉が飛び散る演出を含むため、小さなお子様連れでは安全配慮が不可欠です。
火の粉が飛んで来るので、服に穴が空く(特に化学繊維が危ない)事が考えられますので、注意しましょう。
子連れで観る際に意識したいポイント案としては
- 境内最前列を避け、少し後方または斜め方向から火の動きが見える位置を確保
- 帽子・タオル・目の保護具(メガネやゴーグル)を用意
- 雨天対策/防火・防風服(綿や厚手素材、化繊を避ける)
- 子どもの視線・足元確保:階段や段差、観客の陰にならない位置を選ぶ
- 出店近辺に比較的安全な通路を確保しておく(混雑避け、緊急退避ルート確保)
ケベス祭、火の粉ばっちり浴びてきた pic.twitter.com/EdxzXyYofY
— 鳥居 (@shinmeitorii1) October 14, 2023
地元推薦・隠れスポットはある?
公的資料では「地元推薦の隠れ観覧スポット」「静かな参道」「狙い目時間帯」などの案内は記されていません。
ただし、地元体験者情報としては、
- 出店は多くないという書き手の記録があり、「屋台が多数並ぶ“お祭りフェス”のような規模ではない」印象を持った。
- トウバの準備をする場所(庭やトウバ元家)で神饌の準備を見せてもらった。
- 参道の位置・社殿後方・社境界付近など、視線を遮るものが少ない場所が観覧に適する。
などの情報があり、これらを踏まえ、「隠れスポット案」として提案させて頂きますと、
- 社殿正面だけでなく、参道沿いや社殿裏手の通路を試してみる
- トウバの準備・儀式を行う家(トウバ元)周辺を許可を得て観察する可能性
- 早めに現地入りして用意された出店・機材設置エリアを確認しておく
- 地元観光案内所・文化財課に最新の案内図を聞いておく
というところです。
ケベス祭を最大限楽しむためのポイント
ケベス祭をより安全かつ印象深く楽しむためには、以下のような心構えや準備が効果的です
- 早めの到着・下見
特に観覧位置や人の流れを見ながら動ける時間を確保するため、できれば夕方より前に現地入りして周辺を観察する。 - 服装・防護装備
厚手・綿素材の服、長袖、帽子、タオル、眼鏡・ゴーグルなどを用意。
化学繊維素材は火の粉に弱いため避ける方が安心です(体験記にこの注意が多数見られます) - 体調・装備の準備
夜になると冷え込むこともあるため防寒具を用意。
混雑・歩行を見越して歩きやすい靴が望ましい。 - 情報収集
祭り直前には国東市・文化財課・観光案内所に連絡し、最新の案内図・アクセス図・出店情報を入手。
可能であればパンフレットを手に入れておく。 - 安全確保と逃げ道確保
火の粉が飛ぶ方向や動線を頭に入れて観覧位置を選ぶ。
混雑時には早めに離脱できる通路を確保。 - 心構え・コミュニケーション
地元の人々や参加者と会話を交わし、祭りの由来や伝承話を聞くことで、体験に深みが増すでしょう。
また、祭りの進行に合わせて臨機応変に位置を変えたり、火の動きを追う姿勢が楽しさにつながります。
ケベス祭2025のアクセス方法と駐車場情報
公共交通機関での行き方(バス・乗り換えを使うルート案)
ケベス祭が行われる櫛来社(岩倉八幡社)は、鉄道駅から直接アクセスできる位置にはありません。
そのため公共交通を使う場合はバスおよび徒歩の組み合わせが原則となります。
以下は確認できたアクセス案です。
- 日豊本線「杵築駅」から車で約1時間40分、またはバス利用 → 大分交通バス「国東」行に乗り換え → “伊美行”に乗車 → 「古江」バス停下車 → 徒歩で会場へ向かう案が紹介されています。
- イベントツアー案内では、大分駅・別府駅から観光バスを使うルートが設定されており、「くにみ農産加工駐車場」到着後徒歩10分で櫛来社へ向かう行程が含まれています。
- 最寄りのバス停(古江、櫛来、宮道など)から会場までは徒歩10~13分程度という情報も見られます。
ただし、これらはあくまで公開案内やツアー案内に基づく「アクセス案」であり、当日運行便やダイヤ、乗り換えの有無は変動する可能性があります。
祭り前には国東市・文化財課・バス会社の最新時刻を確認することをおすすめします。
車で訪れる場合・ルートの目安
車で会場を目指す場合、以下のような案を参考にできます:
- 一部案内では、大分空港から約45分ほどで櫛来社へアクセス可能という案内が見られます。
- ただし、会場周辺には狭い道や曲がりくねった道があるため、ナビや地図で事前ルート確認をしておくことが重要です。
- また、祭り当日は交通規制が敷かれる可能性がありますので、国東市の公式情報や交通案内を祭り直前に確認しておきましょう。
駐車場の場所・収容台数・注意点
駐車場についての公開情報を基に、以下のような点に注意が必要です。
- イベント情報サイトでは「駐車場あり30台無料」という案内が見られます。
- ただし、これは十分余裕のある規模とは言えず、満車になる可能性は高いと予想されます。
- 市報では、「駐車場は当分の間、仮囲いをして工事エリアと一般利用者エリアに区画する」旨の記述があり、駐車場の配置・利用可能区画が変動する可能性が示されています。
- 会場の少し手前に駐車可能な場所があった、という旅行記記述もあります。
- 駐車場から会場までは徒歩移動が必要になるケースがあるため、歩きやすい靴・懐中電灯等を準備しておくと安心です。
シャトルバス・臨時交通手段について
公式・公的な案内では、会場へのシャトルバスの運行が必ず実施されるという記述は確認できません。
ただし、観光ツアー案内では「くにみ農産加工駐車場 → 徒歩10分 → 会場」という導線が利用されており、実質的な送迎的役割を果たしているケースがあります。
もしシャトルバスが運行される場合は、定員が限られていることが予想されますので、早めに利用するために余裕を持って行動するのが望ましいです。
周辺施設とのアクセスと利用のヒント
会場周辺には地元商店や飲食店が点在している可能性はありますが、公式に「祭り周辺商店街」が整備されているという案内は見つかっていません。
ケベス祭を見に行くついでに、国東半島の自然・歴史スポット(寺社、海岸、風景地)を巡るルートを組むのも良いと思います。
イベント案内サイトなどでは、行程案の一部として周辺観光地との組み込みが紹介されている例もありますよ。

事前に情報を知っておく事は大切です
ケベス祭2025の混雑状況と快適な観覧のための注意点
混雑しやすい時間帯・場所(予想を含む)
ケベス祭は、宵の時間帯から暗くなった後に最も見どころが展開されるため、夕暮れ以降に人出が増える傾向があります。
市の紹介文には「壮観な火の行事は数時間に及ぶ」と記されており、行事が進むにつれて参拝者が集まる可能性があります。
体験記レベルの観察では、「参加者200人ほどで、決して過密ではなかった」という感想もありますが、これは祭り全体の規模や見物者の入り具合によるものと考えられます。
混雑しやすいであろうエリアとしては、以下が挙げられます
- 境内付近:火を灯すシダの積まれた場所、ケベスとトウバが対峙する場所は目立つ場所となるため人が集中しやすい。
- 火の粉が飛び散る範囲:ケベス・トウバが火のついたシダを振り回したり、動き回ったりする範囲。
観客が近づきすぎるほど熱さ・火の粉の危険性が高まる。 - 観客の動線上:見物者同士が立ち位置を変えたり、火の進行方向に移動したりする流れが混雑感を強める可能性がある。
お子様連れの場合は、混雑が激しくなる時間帯を避けつつ、安全な後方・斜め位置から観覧できる場所を確保しておくのが良いでしょう。
混雑を避けるための事前準備と心構え
快適にケベス祭を楽しむためには、以下の準備が有効です:
- 早めの到着:行事のクライマックスが始まる前に会場入りをし、比較的空いている時間帯に観覧位置を確保する。
- ルート把握:会場周辺の参道や通路を事前にチェックし、混雑を避けやすい道を頭に入れておく。
- 飲み物・タオル等の備え:人込み・熱気に備えて、飲料・タオル・ウェットティッシュを携行しておく。
- トイレ・屋台位置確認:屋台やトイレの位置を早めに把握しておけば、混雑する時間に移動で困ることが少なくなる。
- 服装・身の安全対策:化学繊維の服は火の粉で燃え移る可能性が指摘されているので、綿や厚手素材を選ぶのが無難です。
帽子、眼鏡・ゴーグル、長袖なども有効な防護具となります。
ベスト到着時間と観覧移動戦略(案)
観覧開始前後の時間帯をうまく使うには、以下のような戦略が考えられます
- 目安到着時間:祭り開始直前(18時30分)より早め、たとえば17時半〜18時前には到着しておきたい。
これにより屋台を見て回る余裕もできます。 - 先行ポジション確保:開始直前に境内近くの見通しの良い位置を取る。
ただし、その後火の動きに応じて少し後方や安全な場所に移動できる余裕を持っておく。 - 分散観覧戦略:混雑ピーク時(火の粉散布など)には、最前列より少し離れた場所に移動して、視界と安全性をバランスさせる。
- 穴場時間帯活用:17時台や儀式の前段階(火を灯す直前など)は比較的ゆとりがある時間帯となることが期待されます。
この時間に見所を押さえておくとよいでしょう。
安心して楽しむための持ち物リスト
以下は、混雑・火の粉・夜間観覧などを見越したおすすめ持ち物リストです
- 燃えにくい生地(綿・厚手素材)の長袖・長ズボン
- 帽子、バンダナ、タオル
- 飲み物(長時間滞在を見据えて)
- ウェットティッシュ・ハンカチ
- 防寒具(夜の冷え込みに備えて)
- 小型レジャーシートや折りたたみチェア(場所確保用)
- 滑りにくく歩きやすい靴
- 眼鏡・ゴーグルなど目の保護具
- 懐中電灯や手元灯(暗くなる時間帯の移動用)
- カメラ・スマホの防護(火の粉対策カバー等)
注意すべき点・留意事項
混雑具合は年によって異なり、参加者数・天候・アクセス事情で大きく変動します。
「混雑しなかった」という声もある一方、ニュースでは「参拝者が火の粉をかぶって悲鳴が上がる」という描写も聞かれます。
火の粉の飛散範囲や熱さなどの危険性を考え、観覧位置は余裕を持って選ぶことが望ましいでしょう。
動線が混みやすくなるタイミング(ケベスの突入、火の粉散布直後など)では、観客同士のぶつかり合いや混乱が起きやすくなる可能性があります。
万一近づきすぎて熱を感じたら距離を取る、安全な退避ルートをあらかじめ確保しておくことが賢明です。
祭り公式・市役所・文化財課が当日または直前に発表する混雑案内・制限情報を必ず確認してください。

ケガだけは無いようにしよう!
まとめ
いかがでしたか?
今回は、「ケベス祭2025屋台・穴場スポット徹底調査!アクセス方法や駐車場情報もまとめ!」と題して、2025年のケベス祭についての情報をお伝えしました。
ケベス祭は、大分県国東市国見町櫛来で毎年10月14日に開催される奇祭として知られています。
国の選択無形民俗文化財にも指定されており、その独特な儀式や火祭りとしての迫力は多くの人を魅了しています。
ケベスとトウバが火を巡って繰り広げるユニークな儀式をはじめとし、観客も巻き込む賑やかでスリリングな雰囲気が大きな特徴です。
また、会場では地元ならではの屋台が並び、地域の味覚を楽しめるのも魅力のひとつです。
穴場スポットも豊富にあり、混雑を避けつつゆったりと観覧できる場所も存在します。
アクセス方法も充実しており、公共交通機関や車でのアクセス手段が用意されています。
ただし駐車場は混雑が予想されるため、シャトルバスや早めの到着などの対策を講じることをおすすめします。
また、燃えにくい服装や持ち物の準備など、安全面への配慮も重要です。
ケベス祭は地域の文化を体感しながら、家族や友人と特別な時間を過ごせるイベントです。
火にまつわる神秘的な儀式、地元グルメが楽しめる屋台、そして隠れた穴場スポットまで、多くの魅力が詰まっています。
ぜひ参加者目線で事前に情報を収集し、快適に楽しむための準備をしてみてはいかがでしょうか。
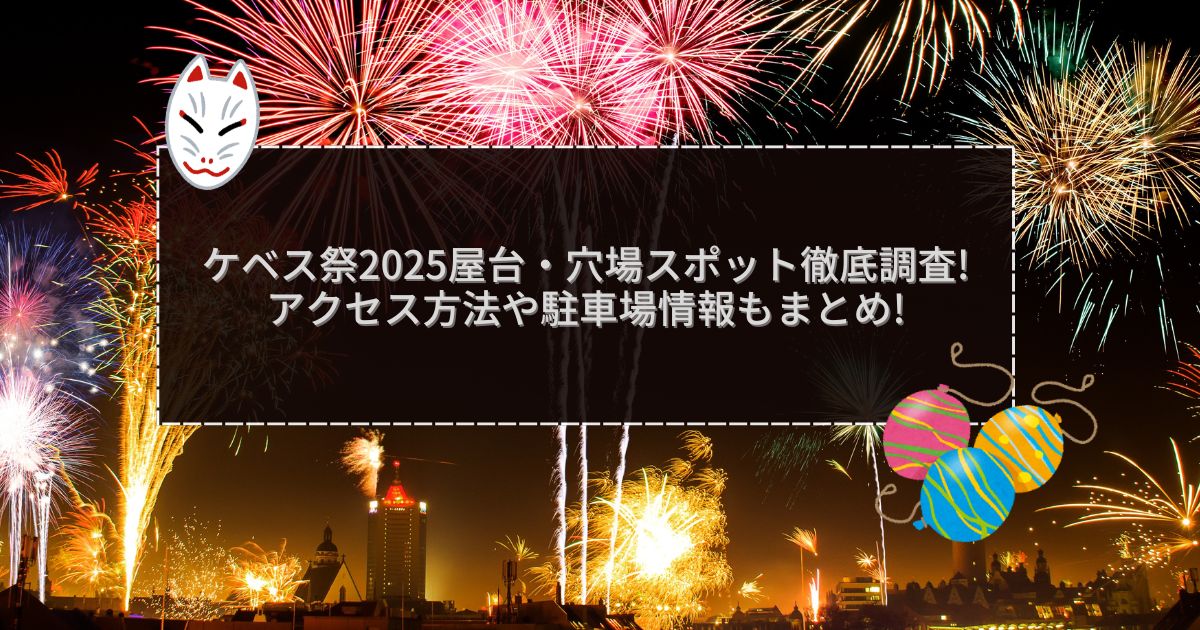


コメント