お祭り好きの皆様こんにちは!
今年も熱いお祭りの季節になりました。
日本全国でお祭りが開催されるていますが、今回は愛知県刈谷市で開催される【刈谷万燈祭】についてご紹介いたします。
歴史ある2025年の刈谷万燈祭は7月26日・27日に開催されますが、笛や太鼓の賑やかな中で万燈がゆらめく景色は、夏の思い出にはぴったりだと思います。
個人的には美しい景色のイメージがありますが、やっぱり屋台が気になりますので、屋台の情報やお祭りの穴場スポットなども調べましたので、お楽しみに!
刈谷万燈祭とは?歴史と背景
江戸時代から続く伝統祭りの魅力
刈谷万燈祭は、愛知県刈谷市で江戸時代から続く伝統的な祭りです。
その起源は18世紀に遡り、地域の歴史と深く結びついています。
この祭りでは、地元住民が誇りを持って作り上げた「万燈(まんど)」と呼ばれる大型の張子人形を担ぎ、お囃子に合わせて勇壮に舞う様子が特徴的です。
多くの観客がその迫力と美しさに魅了されることから、「天下の奇祭」とも称えられています。
刈谷万燈祭 #7月を写真4枚で振り返る pic.twitter.com/lQXhZ2pwyB
— おおたに。┃日本の歴史を彩る風景写真 (@ohtani_tani25) July 31, 2024
秋葉社の祭礼としての由来
刈谷万燈祭は、愛知県刈谷市銀座にある秋葉社の祭礼として始まりました。
五穀豊穣、火難防除、町内安全を祈願することを目的とした祭りであり、長きにわたり地域に根づいてきました。
宝暦6年(1756年)に秋葉堂(現在の秋葉社)が建立され、その後、安永7年(1778年)の古文書には万燈の記述が見られることから、少なくとも200年以上前から続いていることがわかります。
さらに、嘉永5年(1852年)の雨乞い祈願に万燈が使用された記録もあり、祭りの歴史と神社の信仰が深く結びついています。
愛知県無形民俗文化財の指定と評価
刈谷万燈祭は、その地域性と文化的価値が高く評価され、愛知県の無形民俗文化財に指定されています。
伝統を守り続ける町の人々の協力や、毎年新作の万燈を作り上げる技術の継承がこの評価に大きく寄与しています。
また、祭りの際には2日間で10万人以上の観客が訪れるほどの人気を誇り、地域振興にも大きく貢献しています。
その結果、地域の誇りとしてだけでなく、観光資源としても重要な役割を果たしています。
名前の由来「万燈(まんど)」とは
「万燈(まんど)」という名称には、竹と和紙を用いて作られる大型の張子人形が持つ象徴的な意味が込められています。
高さ約5メートル、幅約3メートル、重量約60キロにもなる壮大な万燈は、武者絵や歌舞伎絵など色鮮やかで緻密なデザインが施されています。
この「万燈」という言葉は、無数の灯りが輝く様子を連想させ、祭りの夜を幻想的に彩る象徴として用いられています。
昼の豪快な舞いと、夜の美しくライトアップされた万燈の光景が合わさることで、祭り全体が一層魅力的なものとなっています。
刈谷万燈祭の見どころは?
迫力満点の万燈舞い
刈谷万燈祭の最大の見どころは、なんといっても若衆による迫力満点の万燈舞いです。
高さ約5メートル、重さ約60キロにもなる万燈を若衆たちが一人で担ぎ、笛や太鼓のお囃子に合わせて激しく舞う姿は圧巻です。
その力強い動きと一体感のあるリズムは、観客をぐっと引き込みます。
万燈には武者や歌舞伎のデザインが施され、美しい伝統の造形美とダイナミックな舞の融合が祭りの魅力を一層引き立てています。
夜空を彩る万燈の光と音楽
日が沈むと、万燈に灯りがともされ、夜の刈谷の街を幻想的に照らします。
和紙越しに漏れる柔らかな灯りは万燈の繊細な細工を浮き彫りにし、昼間とは違った美しさを楽しめます。
太鼓と笛のお囃子の音色が加わり、光と音楽が調和した祭りの雰囲気は、夏の風物詩として観客の心を揺さぶります。
この時間帯は写真映えも抜群なので、幻想的な光景をカメラに収めるのもおすすめです。

刈谷万燈祭は夜に映えるお祭りだよね
地域住民と観客の一体感
刈谷万燈祭は地域住民と観客が一体となって盛り上がる祭りです。
参加する7つの町ごとに作られる新作の万燈には、地域の誇りと情熱が込められています。
見物客も、若衆たちが舞う万燈に声援を送り、一体感を楽しみます。
また、町々の皆さんが温かく迎えてくれるため、地元の雰囲気に溶け込みながら楽しむことができます。
この祭りならではの地域のつながりを感じる瞬間は、訪れる価値をさらに高めています。
奉納舞のスケジュールとルート情報
刈谷万燈祭は2日間にわたり、新楽と本楽のスケジュールで進行されます。
新楽は初日(16:30~22:00)
本楽は2日目(16:50~22:00)
に開催され、それぞれ秋葉社を中心に奉納舞が展開されます。
また、各町の万燈が銀座通りや秋葉社周辺をめぐりながら舞を披露するため、ルート上では間近で万燈舞いを楽しむことができます。
開催日程とアクセス情報
刈谷万燈祭は、例年2日間開催される夏の風物詩です。
2024年は7月27日(土曜日)と28日(日曜日)に開催されましたが、2025年は7月26日(土曜日)と27日(日曜日)に予定されています。
祭りは夕方から夜にかけて盛り上がり、新楽は16:30~22:00、本楽は16:50~22:00に行われます。
アクセスは非常に便利で、名鉄「刈谷市」駅から徒歩約5分、またはJR・名鉄「刈谷」駅から徒歩約15分ほどで会場に到着できます。
秋葉社周辺を中心に、刈谷市の中心部が祭り一色に染まります。
駐車場情報と交通規制の注意点
祭りの期間中、多くの観光客が訪れるため、市内の一部では交通規制が実施されます。
車で訪れる場合は、公共の駐車場を事前に確認することをおすすめします。
駅周辺には有料駐車場がいくつかありますが、混雑が予想されるため早めの到着を心がけましょう。また、可能であれば公共交通機関を利用するとスムーズに会場までアクセスできます。
実際の交通規制はこちら
混雑回避のためのヒント
刈谷万燈祭は例年約10万人以上が訪れるため、とても混雑します。
ゆっくりと楽しむためには、混雑する時間帯を避けるのがポイントです。
例えば、17時前後の比較的早い時間に会場入りすると、混雑を避けてゆっくり万燈や屋台を楽しむことができます。
また、撮影に人気のスポットやルートは混み合うことが多いので、事前に穴場スポットをリサーチしておくのが良いでしょう。
帰りの時間帯にも混雑が集中するため、帰路を早めに計画するか、徒歩圏内の駅を利用することをおすすめします。
刈谷万燈祭の屋台とグルメ情報
人気屋台グルメ
- みたらし団子、焼きそば、唐揚げ、イカ焼き
- かき氷(地元店の手作りシロップが人気)
- チョコバナナやくじ引き屋台も充実
特に人気の屋台は18時ごろから混雑し始めるため、17時台に訪れるのがおすすめです。
万燈祭の屋台についてお問合せがありますが、地図のカキ氷のイラストの場所(2カ所)に出ています🍧#刈谷 #刈谷市 #万燈祭 #屋台 #夏祭 pic.twitter.com/ZcWlfTVmxD
— 刈谷市観光協会 (@kariyakankou) July 30, 2022
地元の味を楽しめる屋台の魅力
刈谷万燈祭では、地元の味を堪能できる屋台が勢揃いします。
刈谷市ならではの食材や調理方法を活かしたメニューが豊富で、地元の方々が丹精込めて用意した料理を味わえるのが最大のポイントです。
屋台が立ち並ぶ様子は祭りの活気をさらに盛り上げ、訪れる人々に郷土のぬくもりを感じさせます。
訪れるべきグルメの代表例
祭りでぜひ試していただきたいのが、地元特産のグルメです。
たとえば、香ばしい味噌を使った串焼きや、刈谷ならではの新鮮な海鮮を使った料理が人気を集めています。
また、地元農産物をふんだんに使った握り飯も好評で、多くの訪問客が列を作るほどの賑わいを見せます。
お祭り限定の創意工夫されたメニュー
刈谷万燈祭ならではの楽しみとして、祭り限定の特別メニューがあります。
たとえば、万燈をモチーフにしたスイーツやドリンクなど、SNS映えするオリジナルのメニューが訪れる人の目を惹きます。
これらの創意工夫されたメニューは、地元の協力によって毎年新しい工夫が凝らされ、祭りの楽しみをさらに広げてくれます。
地元産の素材を活かした逸品
刈谷万燈祭の屋台では、地元産の新鮮な素材を活かした逸品を楽しめます。
地元で取れた新鮮な野菜や魚介類は格別の味わいで、訪れる人を虜にします。
こだわりの調理法や伝統の味付けが、地元食材の持つ旨味をさらに引き立てています。
刈谷万燈祭2025の穴場スポット
毎年多くの人で賑わう刈谷万燈祭ですが、ゆっくり楽しみたい方のためにおすすめの穴場観覧スポットを3つご紹介します。

自分だけの穴場スポットを見つけるのも楽しいかも
亀城公園(かめきこうえん)
市原稲荷神社から徒歩約10分。
木陰も多く、芝生に座ってのんびり過ごせるスポット。
夕方からは祭りの音も聞こえて雰囲気も良好。
セントラルパーク(刈谷市役所近くの公園)
人通りが比較的少なく、屋台の帰り道に立ち寄る人も少なめ。
照明もあり夜も安心です。
ミササガパーク(猿渡公園)
会場からやや離れているものの、広々とした芝生エリアと展望丘があり、夜風を感じながらの休憩に最適です。
家族連れに人気です。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、「刈谷万燈祭2025の屋台と穴場スポット情報まとめ!見どころもまとめ!」と題して2025年の刈谷万燈祭の情報を屋台や穴場スポットを中心にお伝えしました。
刈谷万燈祭は、歴史ある伝統文化と現代のにぎわいが融合する夏の風物詩です。
2025年は7月27日と28日に開催予定で、屋台も多数出店され例年以上の盛り上がりが期待されます。
混雑を避けて楽しむには、屋台は17時ごろから楽しみ始め、19時以降は穴場スポットに移動するのがベスト。
今回紹介した情報を活用して頂いて、落ち着いて祭りを堪能してください。
地元グルメと伝統の融合を、ぜひ体験してみてください。
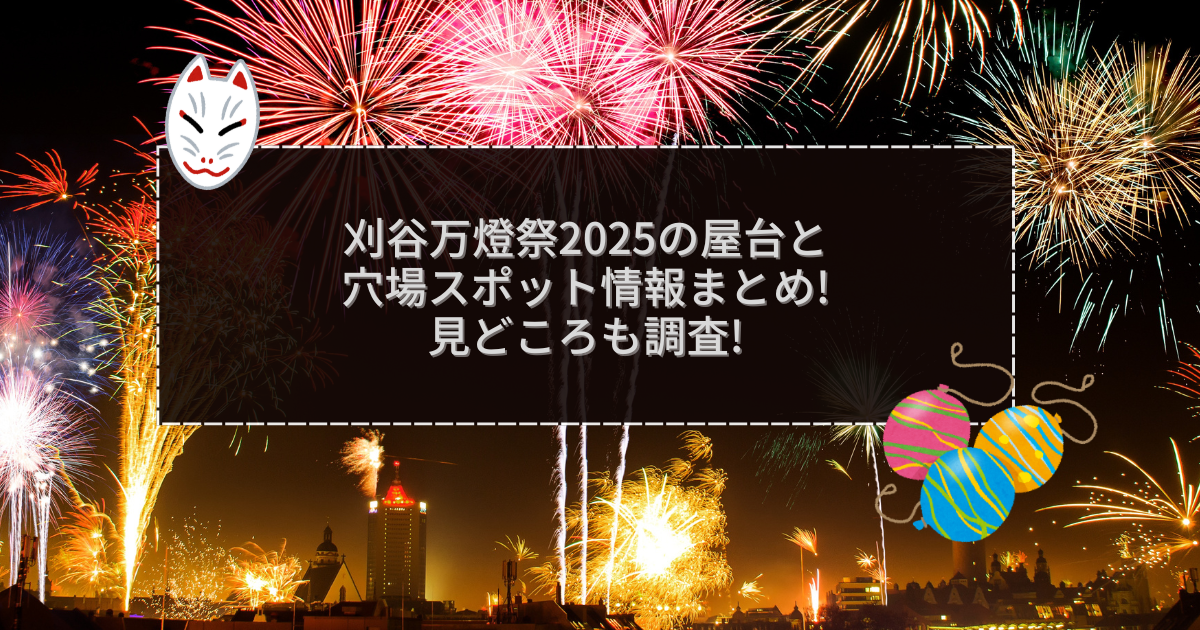


コメント